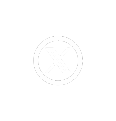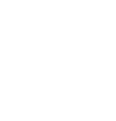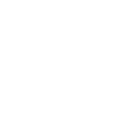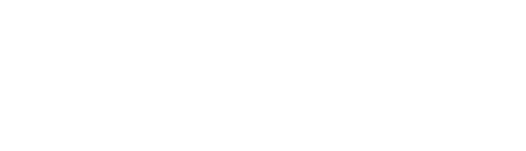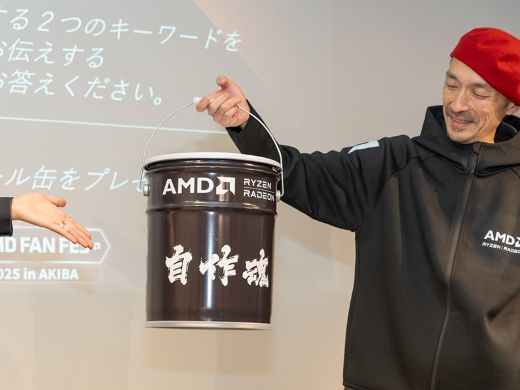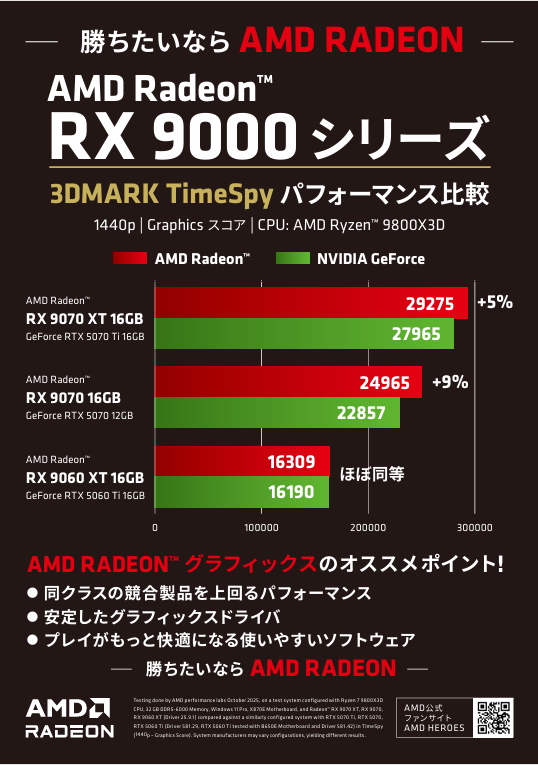進む道を違えたAMDとNVIDIA
検証編へ進む前に、Radeon VIIはWindows10 October 2018 Updateより追加されたDirectX Raytracingこと“DXR”、そしてDLSS対応にも触れておきたい。今のところこの2つの技術に対応しているのはNVIDIAのRTX 20シリーズだが、Radeon VIIはこのどちらにも対応しない。
まずDXRは理論上Radeon VIIでもFallback Layerを利用してレイの衝突判定を実行させることが可能だが、専用ハードではないためスループットに難はあるし、何よりAMDはまだRadeonにDXR対応は時期尚早と考えている。DLSSはNVIDIAの機械学習とTensorコアありきの技術である以上非対応なのは当然の話だ。
だがこれは実際ゲーマーにとって大したデメリットではない。RTX 20シリーズの最大の武器であるDXR対応もBattlefield V以外のゲームが一向に増える気配がなく、DLSSに関してもゲーム側の実装が着々と遅れているのは事実だ。
一部ゲームで最新グラフィック技術を堪能できなくなるというデメリットはあるが、むしろゲームで高パフォーマンスを得られれば良い、と考えているユーザー向けの製品といえる。さらにAMDは映像編集、特に4K以上の高解像度なメディアを扱うクリエイター向けの製品としてもRadeon VIIを推している。HBM2のパフォーマンスはゲームはもとより、GPU支援を必要とするクリエイティブ系アプリにも効くのだ。

実は今回プレス向けに配布されたRadeon VIIのアピールポイントをまとめた資料には、ゲームよりもクリエイター向けのアピールポイントが熱く語られていた。図はDavinci Resolve 15で8Kのカラーグレーディングをする時のパフォーマンス比較。VRAMがリッチなRadeon VIIが速いと訴えている
高パフォーマンスを得るためには高クロックで回るGPUコアと、高速なメモリーバスと潤沢なVRAMが必要になる。そのためには7nmという技術的アドバンテージが必須になる。今後10年で培わなければならない描画手法(反射ばかりが取り上げられるが、レイトレーシングは複雑になりすぎたシェーダープログラミングからの開放を意図した技術だ)を採用したのがNVIDIA。
そうした場合、既存の設計を最大限活かし設計コストを抑えつつ、最大の性能ゲインを得るためにプロセスでのアドバンテージを選んだのがAMDとなる。これまで両社は片方が何かに挑戦すれば、片方も応戦する形で発展してきたが、今回はあえて異なる成長戦略をとることで活路を見出した訳だ。


ただ、これはAMDの苦しい現状の裏返しでもある。前述の通りRadeon VIIは業務向けの演算処理に特化させたRadeon Instinct MI50アクセラレーターをコンシューマーに下ろしたもの。NVIDIAで言えばQuadroやTesla的なポジションの製品をいきなり下ろしてきた訳である。本来高価な値段で売れるものをギリギリの値段で売るとなれば、大いなる機会損失にもなる。
この理由はやはり“AMDには今打てる手がない”ことに尽きるだろう。より設計の進んだ“Navi”がまだ出せないし、かといってこのままハイエンド領域をRTX 20シリーズの思うままにさせる訳にもいかない。
苦し紛れで投入を決めたのがRadeon VIIなのではなかろうか。CES 2019で突然製品をお披露目したり、UEFIでブートしないBIOSを組み込んだままカードを出荷したのも、こうした背景があるからではなかろうか。